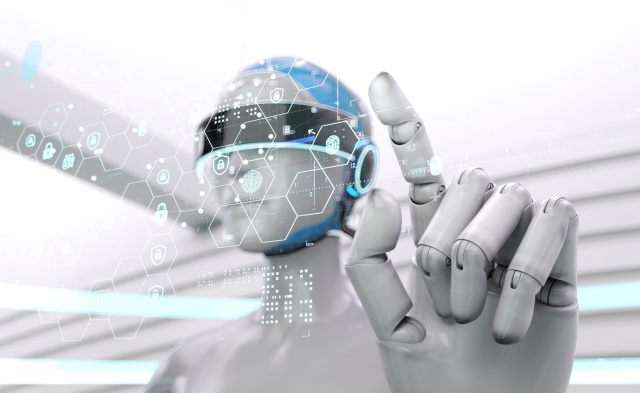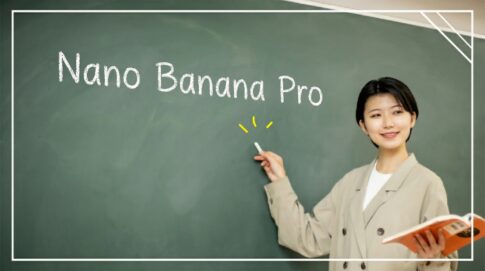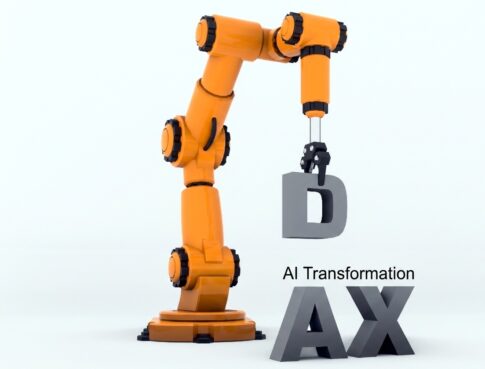最近、約2万人が署名したという、超知能(人間の知能を大きく超える可能性のある人工知能)開発禁止を求める運動が話題になりました。技術革新の“スピード”と“制御”のバランスが、大きな課題になっていると感じます。今回はこの問題を整理し、自社・組織として向き合うべき視点を考えてみました。
運動のコア
まず、今回のニュースが示している“動き”を整理します。
- 超知能の開発を禁止すべき、という署名活動に約2万人が参加しました。
- 背景として、AIの能力が急速に高まり、「人間の知能を凌駕する人工知能が出てくるかもしれない」という懸念が広がっています。
- とりわけ注目されているのは、単なるAIではなく、より広い知能・判断力を備えた“超知能”と呼ばれる領域です。
- 署名運動や議論が出る背景には、「もし制御不能な知能ができたらどうなるか(まるでターミネーター?)」「人間の意思決定・価値観がどうなるか」という根源的な問いがあります。
技術発展の先が予期せぬリスクを含んでいるという点が、今回の運動のコアだと言えます。
“超知能”議論は何を意味するのか
では、技術・仕事・社会においてこの“超知能”議論は何を意味するのか。
技術面
- AI技術はすでに多くの業務を効率化・代替しようとする流れにありますが、超知能の領域では、人間のように柔軟に判断・学習・自己改善する能力が想定されています。
- 既存のAI技術とは質が異なり、何を任せるか、もしくは任せないか、という判断基準も迫られます。
- 開発禁止を求める動きが出ているということは、技術推進一辺倒では危ないという社会的シグナルとも捉えられます。
仕事・生活への影響
- 出来るだけの仕事をAIに任せるという視点だけでなく、人間がどこで価値を出すかが重要になってきます。超知能に任せるかどうかの判断、またそのリスク・倫理の議論が仕事の中に入ってくるようになります。
- 組織は、もしAIが予想外に変化したら(シンギュラリティ的な)という前提で、業務プロセス・責任の所在・人材育成を見直す必要があります。
- 社会としては、技術の恩恵だけでなく、技術によって人間の尊厳や意思決定の自由、価値観が脅かされないかを議論する必要があります。
“どう付き合うか・備えるか”
私は、企業を経営する立場から超知能のような技術的な飛躍を怖がるのではなく、“どう付き合うか・備えるか”を前提にすべきだと考えています。以下、自分自身の実感と共に述べます。
- 弊社でもAIの活用を積極的に進めていて、効率化・新サービス創出の可能性を強く感じています。
- 今回の署名運動を見て、倫理面などは追いついていないというギャップを改めて感じました。
- 具体的にどう付き合うか・備えるか(案)
- 技術導入時に“ヒト/AI”の役割を明確化し、AIが誤った判断をした際の体制を設ける。
- 社員・関係者向けに、AIの可能性とリスクの双方を紹介するワークショップを実施する。
- 社外にも、技術倫理・社会的影響について対話できる機会を創る。
- 禁止ではなく制御可能な形・説明可能な形で技術をデザインしていくことが現実的だと思います。技術放任するようなことはリスクだと思いますが、過度な禁止などは、発展・成長の機会損失を生んでしまいますので、やっぱりバランスが重要だと思いますね。
AI活用に悩む経営者・マネージャーの方へ。Web制作の現場を知る、元アートディレクター・営業の視点で、AIの活用方法についてサポートします。
⇒生成AIセミナー・個別相談はこちら