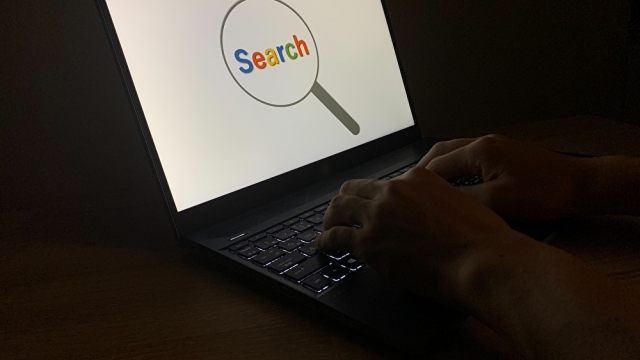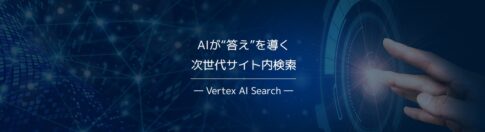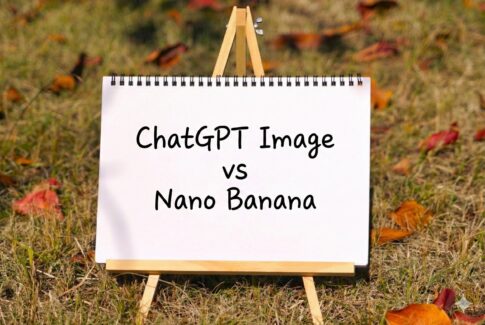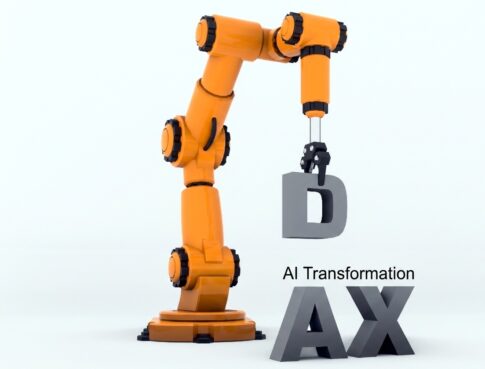2025年10月、GoogleはPrivacy Sandboxの複数APIを廃止すると発表しました。Privacy Sandboxとは、ユーザーのプライバシーを保護しつつ、デジタルビジネスを支援するための技術のことです。Cookie代替の模索は一段落し、現実解へ舵が切られた印象です。経営の現場で何を変え、何を守るのか?要点を整理してみます。
なにが起きたのか
- ChromeはサードパーティCookieの扱いで“現行のユーザー選択を維持”(=全面廃止を直ちに進めない方針)。
- そのうえで、Attribution Reporting、Topics、Protected Audience、Private Aggregation/Shared Storage、IP Protection、SDK Runtimeなど、Privacy Sandboxの中核と目されたAPI群の廃止を予告しました。廃止はプロセスに沿って段階的に進み、開発者サイトで随時案内されるようです。
- 今後は、W3CのPrivate Advertising Technology WGにおける「相互運用可能なアトリビューション標準」など、より標準化・相互運用性の高いアプローチへ注力する方針です。
この動きは、2025年上半期の方針見直し(Cookie UXの再設計見送り)や、英国CMAのコミットメント見直しと地続きです。大型の“置き換え”から、現実的な漸進策へと重心が移りました。
この変化がもたらす影響
技術面(かみ砕き)
- 計測(アトリビューション):ブラウザ専用APIに依存するより、標準化に基づく手法と、サーバーサイド計測(例:サーバー側タグ、コンバージョンAPI)の組み合わせが主軸に。過度にブラウザ独自仕様へ最適化した実装は見直し対象です。
- ID・認証連携:FedCM(以前はWebIDと呼ばれていました)のように、採用が進む領域は継続。ただしサードパーティCookie前提のフローは、自社ドメイン内での完結や同意管理の再設計が必要です。
- 広告配信・最適化:オーディエンス構築は、自社一次データの整備、コンテキスト(ページ文脈)の活用、クリエイティブ検証の地力が問われます。
仕事・組織面(現場の具体)
- 短期:現行のCookie在庫に甘えず、サイトのCookie棚卸し(用途・保存期間・提供先)と代替案の試験運用を並行で。
- 中期:計測基盤の二系統化(ブラウザ依存×サーバー側)でリスク分散。媒体/ツール差異に耐えるモデル監査(計測差の把握と補正)を定常運用に。
- 長期:広告だけに頼らない収益ポートフォリオづくり(会員・サブスク等)。“計測不能でも意思決定できる”KPIの再設計が鍵です。
生活者への影響(やさしい視点)
- ポップアップだらけの同意体験が減る方向に進めば、閲覧体験は静かに良くなる可能性があります。対して“見えにくい計測”が増えると感じる場面もあると思われます。だからこそ、透明性(何を集め、なぜ必要か)の説明力が企業に求められます。
個人的見解としては・・
私の見解としては、今回の方針転換は「魔法の置き換えは来ない」という合図ではないかと思います。テクノロジーの大枠は“標準+一次データ+運用力”にまとまっていきます。ここで勝敗を分けるのは、派手なAPI比較ではなく、
- データの取得根拠(法と同意)が明確で、
- 社内で説明可能なKPI体系を持ち、
- 変化に合わせて実験→学習→改善を回し続けられるか。
最後に。今回の発表は不安よりも自由度の回復ではないでしょうか。ある意味、原点回帰ともいえるのかもしれません。業界全体が相互運用を見据えて進めば、Webはもっとシンプルで強い武器なります。私たちは足場を固め、自分たちで測り、自分たちで学ぶ体制に切り替えていきましょう。