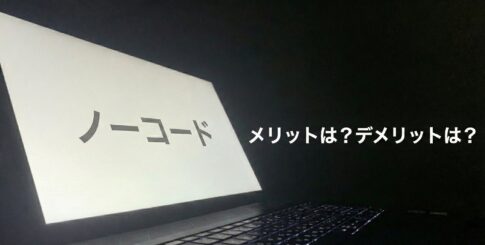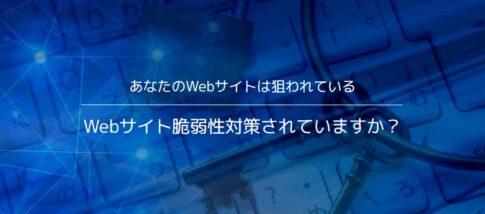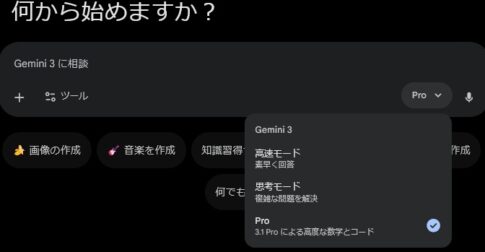「AIで効率化だー!」と張り切って導入したのに、前よりバタバタしている——そんな声を耳にしました。これを生産性パラドックス(Productivity Paradox)と呼ぶそうです。おそらく原因は、本人の性格の問題とかではなく、使い方と仕組みのズレにあります。ここでは、よくあるつまずきと、じゃあどうしたら良いのかを書いてみます。
1. 忙しくなる典型パターン
まずは、あるあるを先に書いてみます。みなさんは心当たりありますか?
- 出力(AIの提案)が増えすぎる
下書き、案、要約が一気に量産され、読む・選ぶ・直す手間が膨らんでしまっている。 - とりあえずAIに頼むことが習慣化している
小さな作業まで、どんどんAIに投げてしまって、確認タスクの山ができている。 - 締め切りが前倒しになる
速く仕上がる分、次の依頼がすぐ来る。結果、常に急ぎモードになる。これはこれで利益が出て良いことですけどね。 - 品質ラインが曖昧
どこまで直せばOKか決めていないので、終わりなき微調整にハマる。これ、心配性あるあるかもしれないです。 - ツールが増殖
目的が似たAIをいくつも使い、入口もデータも分散して迷子になる。これは、結構陥る人がいると思います。
2. 根っこにある、期待のズレ
AIは「作業をゼロにする魔法」ではなく、「作業を作り直す道具」です。
- 以前⇒手を動かして“作る”が中心
- 以後⇒AIの出力を“定義→選ぶ→検品→伝える”が中心
この切り替えをせず、昔のやり方の上にAIを乗せるだけだと、仕事が二重化して忙しくなってしまいます。何を隠そう、私も最初はこれでした。
3. 今日からできるカイゼン
(1) まず“やらないこと”を決める
- タスクごとに、今日のゴールはどこか?を先に決めておく。
- ラフ段階で8割OKなら先へ進む。完璧にするのはあとにする。
(2) プロンプトより“ブリーフ”
AIへの指示文(プロンプト)を工夫する前に、自分の要件メモ(ブリーフ)を整えると迷いが減るはずです。具体的には入れるのは4つだけです。
- 目的(誰に何を届けたいか?なんのために使うものか?など)
- 使いどころ(メール/資料/SNSなど)
- 制約(字数、言い回し、NG項目)
- 品質(ラフレベル/実務レベル/公表・公開レベル)
この4点をAIに渡すだけで、リテイクの回数が減るはずです。他に何か気になるから足す・・と、なかなか終わらなくなってしまいます。
(3) “一発勝負(出力)”をあきらめて、2段階で出力
- 段階1として、骨子(見出し・要点)だけ出してもらう
- 段階2として、骨子が合っていたら中身を膨らませることにする
最初から長文を出させようとすると、読み直しが重くなって大変です。
(4) 時間ではなく回数で区切る
- 例えば「AIの出力結果の修正は3回まで」と決める
- 3回で届かなければ、自分の手で2割程度手直しして次へ進むことにする
終わりが見えると、永遠に悩む(極めようとする完璧)クセが消えます。
(5) “AIに頼む→自動で整理”までを1セットに
- 出力は同じ場所に集める(1つのフォルダ)
- ファイル名に日付_用途_品質を入れるておくと、あとで見返す際に便利
- 週1回、要らないファイルを捨てる時間を確保しておく
(6) 人に渡す前提でまとめる
AI案は、他人が読んで分かる形に整えてから共有する。
- 先頭に「目的・対象・決めたこと」を3行でまとめておくと、相手も読み始めるのが楽。
- 確認してみたけど、真実かどうかあいまいな部分は明記しておく。
4. 仕事の種類別、AIとの付き合い方の目安
- 文章づくり(メール、記事、提案)
→ 骨子→短文→清書の順。清書は時間をかけず、声に出して読んで引っかかる所だけ修正。 - リサーチ(情報集め)
→ 目的・範囲・締め切りを宣言。“出典リンク必須”をセット。最後に自分の一文要約を付けて保存。 - データ整理(一覧化、要約)
→ 入力フォーマットを決め打ち(列名・並びを先に指定)。途中で形式を変えない。 - アイデア出し
→ 数より「違う角度3つ」で頼む。似た案を10個より、偏りのある3個の方が使える。
5. それでも忙しい時は、持ちすぎ!
- 依頼が来るたびに即返してしまう
→ 悪いことではないですが、できれば1日の中にAIタイムを作り、そこでまとめて投げる。 - チャットとAIウィンドウが常に開きっぱなし
→ あるあるですよね。ですので、午前は作業、午後はAI+連絡・報告、など時間を分ける。 - AIの新機能にすぐ飛びつく
→ 新機能を把握することは大事ですが、全部頭に入れるのは無理なので、優先順位をつけて、高い順に飛びつくようにしたほうが良いでしょう。普段の業務で使わないのに、すべてを把握しようとしても、すぐに忘れてしまうかと。
6. 小さな成功体験の作り方
忙しさは感情の問題でもあると思います。一つ一つ、こなしたという実感を得るように仕事を前に進めると気持ちが整うのではないでしょうか。
- 毎朝、AIにやらせる3タスクだけ決める。つまりそれ以外は自分でやる。
- 1日の最後に「AIで浮いた時間でやれたこと」を1行メモをしておく。これ、案外あとで、部下や後輩などに伝える大事なアドバイスのネタになるかも。
AIで忙しくなるのは、ある意味、AIを使いこなすための通過点なのかもしれません。できることが増えて楽しいと思うこともあるので、夢中になっている人も多いかと思います。そんなAIも、いづれは誰もが普通に使いこなすようになって、会話の中にAIの言葉すら聞かなくなるようになるでしょう。その時、私たちは人として、何をやらないといけないのか?が、本当の意味で知ることになるのでしょうね。
AI活用に悩む経営者・マネージャーの方へ。Web制作の現場を知る、元アートディレクター・営業の視点で、AIの活用方法についてサポートします。
⇒生成AIセミナー・個別相談はこちら