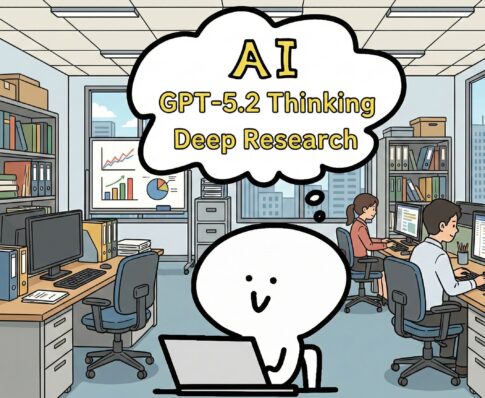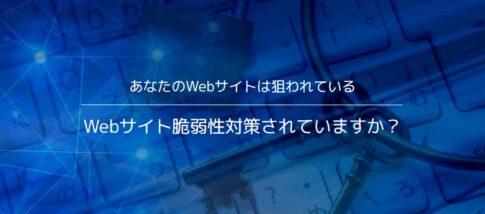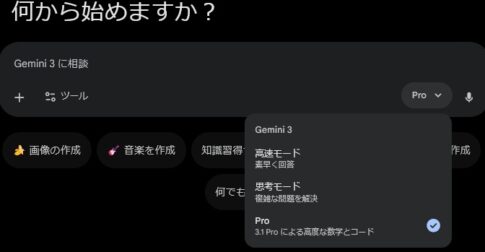Z世代の多くは、ニュースもトレンドもまずSNSでキャッチしますよね。でも、タイムラインには本当のことも、ちょっと怪しい話も一緒に流れてきます。今回は、SNSど真ん中世代だからこそ身につけたい“情報の見極め力”を書いてみようと思います。
最近の流れ的な話
NTTドコモ・モバイル社会研究所の調査によると、ニュースを得るメディアとして、10〜20代ではSNSがトップになりました(今さら感はありますけど)。テレビや新聞よりも、XやInstagram、YouTubeなどのSNS経由でニュースを見る若者が多い、ということです。J-CAST ニュース
同じく国内の別調査では、Z世代は
- 情報収集や動画視聴は「ほぼスマホ」
- 検索サイトよりも、YouTubeや各種SNSをよく使う
- 商品購入前も、まずSNSで口コミやレビューをチェックする
といった傾向がはっきり出ています。n-info.co.jp+1
さらに、ICT総研の調査では、日本全体でも約9割が何らかのSNS・コミュニティサービスを利用していて、YouTube・X・Instagram・TikTokといったサービスの利用率は年々増加傾向です。ICT総研
良くも悪くも、「ニュースサイトにアクセスする」というより、「SNSを眺めていたら、ニュースも一緒に流れてくる」というのが、当たり前のような状況になっている、ということなのでしょうね。
Z世代が置かれている状況
1. SNSニュースの「いいところ」
まずポジティブな面から。
- スピードが速い
地震・事故・イベントの速報などは、テレビよりSNSの方が早く流れてくることも多いです。 - 多様な声が見える
一般の人の体験談や、マイノリティの視点、現場のリアルな声が届きやすいのは、SNSならではの強みです。 - 自分に合った情報が集まりやすい
アルゴリズム(その人の行動から「好きそうな投稿」を選んで見せる仕組み)のおかげで、興味のあるジャンルのニュースが自然と集まってくる、という良さもあります。
Z世代のマーケティング調査を見ても、
「新しいモノを買う前はSNSの口コミを見る」
「トレンドは主にSNSで把握している」
と答える人が多く、生活とSNSがかなり強く結びついています。Deloitte

2. でも、リスクも同じくらい大きい
一方で、SNS時代ならではのリスクもはっきりしてきています。
- 偽・誤情報(フェイク)が広がりやすい
国内外の調査で、SNS上の偽情報・誤情報が政治や経済、健康などに大きな影響を与えうることが指摘されています。日本ファクトチェックセンター (JFC)+1
「バズれば勝ち」という空気があるぶん、煽り気味の投稿や、事実より感情を刺激する情報が拡散されやすいのも事実です。 - アルゴリズムによる「偏り」
似た意見ばかりがタイムラインに流れてくる現象は、よく「フィルターバブル」「エコーチェンバー」と呼ばれます(自分と同じ意見だけが反響して返ってくる部屋、というイメージ)。
見たいものだけ見ているうちに、別の視点があることに気づきにくくなる、という問題があります。 - インフルエンサーが「ニュースの窓口」になっている
海外の調査では、ニュースをインフルエンサー経由で受け取る人が増えていることが報告されていますが、彼らは新聞社やテレビ局ほど厳密なチェック体制を持っているわけではありません。AP News+1
もちろん優れた情報発信者もたくさんいますが、「フォロワーが多い=情報の質が高い」とは限らないのが難しいところです。 - 生成AIで「それっぽい嘘」も作れてしまう
文章も画像も動画も、AIでかなりリアルに作れるようになりました。便利な一方で、見た目だけでは真偽が判断しづらい 時代になっています。
3. じゃあ、どう身を守ればいい?
ここからが本題の情報リテラシーです。難しく言うと「情報を集める・見分ける・使う力」。個人的には、次の5つを意識するだけでもだいぶ違うと感じています。
- 「1ソース依存」をやめる
- SNSの投稿を見たら、公式発表や信頼できるニュースサイトなど、別の情報源も1つは必ず確認する習慣をつける。
- 「誰が言っているか」を見る癖をつける
- 匿名か実名か、個人か組織か、専門分野と関係のある人か、完璧に見抜く必要はなくて、「この人はどんな立場で話してるんだろう?」と一歩引いて見るだけでも、受け取り方は変わると思います。
- 感情が揺さぶられたときほど、一呼吸おいてみる
- 怒り・不安・不快感を強くあおる投稿は、バズりやすい分、誤情報も混ざりがちです。例えば、「え、マジで?」と思ったら、その場で拡散せずにスクショしておいて、あとで落ち着いて調べるくらいがちょうどよいのではと思います。
- 「3つ自問してからシェアする」自分なりのルールを持つ
例えばこんな感じですね。- 1)この情報の元ネタはどこ?(誰の何の記事?)
- 2)似た内容を他のメディアも報じているか?
- 3) 自分がこれを拡散したら、誰かを傷つけたり、迷惑をかけたりしないか?
- AIの答えも「1つの意見」として扱う
生成AIのチャットボットや要約サービスも、ニュースを理解する助けになります。でも、情報源が明示されているか、他のメディアと内容が矛盾していないか、などは、やっぱり自分でも確認した方が安心です。
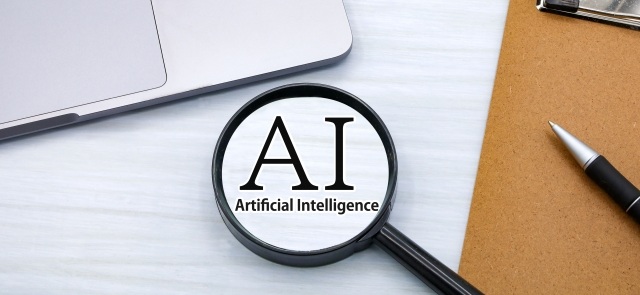
Z世代は、情報リテラシーが低いのではない
私自身、デジタルマーケティングの仕事をしていて感じるのは、Z世代は情報リテラシーが低いのではなく、「新しいリテラシーを求められている」ということです。
テレビと新聞だけが情報源だった時代と比べて、いまは1日に触れる情報量がケタ違いで、公式・個人・AIがごちゃ混ぜで流れてきて、情報だけでなく感情までタイムラインに乗って流れてくる環境下に私たちは置かれているはずです。とってもハードな環境ではないかと思います。
だからこそ、全部を追うのではなく、自分にとって大事なテーマを決めて、そのテーマについては、信頼できる情報源をあらかじめいくつか登録しておき、SNSやAIなどは、あくまできっかけであって、入り口として使うという、情報との付き合い方ができること、それが必要とされるリテラシーなのではないかと思います。
Z世代のみなさんは、スマホもSNSも、ある意味「母国語」みたいなものかと。そこに少しだけ仕組みを理解する力と、ひと呼吸おく癖が加われば、情報の洪水はかなり穏やかに見えてくるはずです。
SNSやAIは、Z世代にとって強力な武器にも、ストレスのもとにもなりうる存在です。情報との距離感を自分で選べるようになっていきましょう。