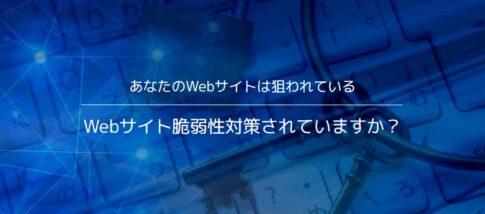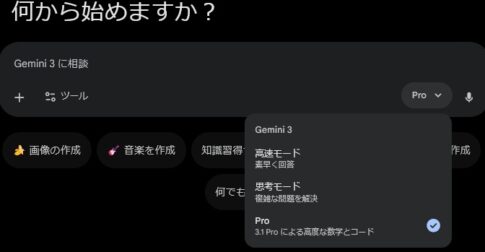山や里などで出没するクマのニュースを見ない日は、ほとんどなくなってきました。
こうした事態を受けて政府は11月14日、「クマ被害対策施策パッケージ」を改定しました。これは、国民の安全・安心の確保、そして人とクマ類のすみ分けを図ることで、クマ類による被害を抑制することついてまとめられたものです。
ここでは、専門用語をできるだけかみくだいて、「結局、私たちの生活にどう関係するの?」という視点で整理してみます。
なぜ今、「クマ対策パッケージ」なのか
まず背景です。
- 2025年度、クマに襲われて亡くなった人は、すでに13人と統計開始以来最多。2023年度の2倍以上になっています。株探
- 今年4〜9月のクマの出没件数は約2万件で、昨年度1年間の件数をすでに上回りました。株探
エサとなる木の実が山で不足すると、クマは柿の木や畑、ゴミなどを求めて人里に近づきやすくなります。人口減少で人の少ない集落が増え、草刈りや柿の木の手入れが行き届かなくなっていることも、クマが里に下りやすい環境につながっています。
こうした状況を受け、政府は2024年4月に「クマ被害対策施策パッケージ」を作成し、その後も見直しを続けてきました。クマを指定管理鳥獣として位置づけ、国・自治体が連携して管理する枠組みを整えています。環境省+1 今回の改定は、その強化版というイメージですね。
ざっくり何をするの?
政府の資料を見ると、細かい項目がずらっと並んでいて、正直かなり難しい内容です。環境省+1 住民目線で整理すると、主に次の5つの柱があると思います。
1 そもそもクマを生活圏に近づけない対策
- 放置された柿の木など、「クマを引き寄せるエサ」の片づけを進める支援
- 住宅地や集落の周りに、草やヤブが生い茂らない「緩衝帯(見通しの良い帯状エリア)」を整備
- 電気柵の設置や、農地周辺の防護柵の強化
- クマが川沿いを通って里に下りにくくなるよう、河川の環境管理を進める
こうした対策を、環境省や農林水産省、林野庁、国土交通省が連携して自治体を支援します。環境省+1
2 クマが出たときに、すばやく・安全に対応する仕組み

- 自治体ごとの「出没対応マニュアルづくり」や訓練の支援
- クマの出没情報を、ICTを使って集めて共有する仕組みづくり
- 住宅地や建物の中にクマが入りこんだときの、銃の使用ルール(鳥獣保護管理法のあり方)について検討
- 警察や自治体が連携して、出没時の交通整理や住民避難など、安全確保を強化
これらは、実際にクマが出たときに「誰が何をするか」を明確にして、混乱を防ぐためのものです。環境省+1
3 クマの数や生息範囲をきちんと把握し、必要に応じて捕獲する

- クマの個体数や生息分布、被害状況などの調査・モニタリングを国が支援
- 人の生活圏の近くで、必要な範囲でクマを捕獲・駆除する取り組みを支援
- 農地周辺でのクマ捕獲を進める
ポイントは、クマを全部いなくするのではなく、地域ごとのクマの個体群を保ちながら、人との距離をとる」という考え方です。環境省+1
4 専門人材「ガバメントハンター」などを増やす

今回の改定で、特に大きく報じられているのがこれです。
- 狩猟免許を持つ人を自治体が公務員として雇い、「ガバメントハンター」としてクマ対策にあたってもらう仕組みを整備
- クマ対応の専門家や、捕獲・麻酔・安全管理の技能を持つ人材の育成・確保を、国が支援
現場で動ける人がいないと、どんな計画も進まない結果になってしまいます。ガバメントハンターを公務員として雇用することで、権限を与え、責任をもって業務にあたるという狙いがあるのだと思います。
5 ドローンやICTなど、新しい技術もフル活用
- ドローンで山の中や広いエリアを見回り、クマの位置を確認
- 出没情報をアプリや地図上で共有し、警戒が必要な場所を見える化
- こうした取り組みを行う自治体に、交付金などで支援
すでに政府の資料でも、「ドローンやICT技術を活用した鳥獣対策」が打ち出されています。内閣府+1
私たちの暮らしはどう変わる?
住民の立場から見ると、今後こんな変化が考えられます(私の期待含みです)。
- 集落の周りの草刈りや、放置柿の伐採などの取り組みが、自治体主導で進みやすくなる
- クマの出没情報が、自治体の防災メール、アプリ、IPデバイス、ケーブルTV、広報車などで、より素早く共有されるようになる
- 学校や保育所、通勤・通学路での見回りが増える可能性
- 「クマが出たとき、誰に連絡すればいいのか?」「どこまでが危険区域なのか?」が、これまでより明確になる
一方で、クマの個体数管理の強化が期待できるため、山での猟銃の発砲音や、捕獲作業を目にする機会も増えるかもしれません。その意味では、「クマから自分の命を守ること」と「自然の中で生きる野生動物をどう扱うか」という難しいテーマに、社会全体で向き合っていく必要があります。
住民一人ひとりができること
国のパッケージができても、最後にクマと向き合うのは私たち一人ひとりです。環境省などが示しているポイントを踏まえると、次のような対策が大切になります。環境省
- エサになるものを外に放置しない
- 生ゴミ、ペットフード、バーベキューの残りなどは外に置きっぱなしにしない
- 放置柿や果樹があれば、できる範囲で収穫・伐採を検討する
- クマが活発な時間帯(早朝・夕方)の単独行動を避ける
- 山菜採りや釣り、散歩、ランニングでも、可能なら複数人で行く
- クマ鈴やラジオ、ホーンなどで「人がいる」ことを知らせる
- クマの最新情報をチェックする
- 自治体のホームページや防災メール、掲示板などで出没情報を確認
- 「この辺は最近出ていないから大丈夫」などと油断しない
- クマを見つけても、近づかない・写真を撮ろうとしない
- 子グマの近くには必ず親グマがいます。かわいく見えても、絶対に近づかない
- クマに限らずイノシシ、サルなども同様です。
- クマを見たら、自治体や警察に連絡する
- 「こんなことで電話していいのかな?」と遠慮せず、位置・時間・頭数などを落ち着いて伝える

「怖い存在」だけで終わらせないために
クマは、もともと日本の森の頂点に立つ生きものです。クマがいること自体は、森の豊かさの証でもあります。一方で、人の命が失われている現実もあり、「怖いから全部いなくしてしまえ」という声が出てくるのも無理はありません。今回のクマ対策パッケージは、その間でなんとかバランスを探ろうとする試みだと言えます。環境省+1
大事なのは、「クマが悪い」「山に入る人が悪い」と誰かを責めるよりも、
- どこまでが人の生活圏で
- どこからがクマの生活圏なのか
その線引きを地域ごとに考え、具体的な対策に落とし込んでいくことだと思います。
国のパッケージは、そのための道具箱のようなもの。この道具箱をどう使うかは、自治体と地域住民、そして山や森と関わる人たちの話し合いにかかっています。「クマがいるから、もう山には行かない」ではなく、「クマと人、両方が生きていける地域にするには、何ができるだろう?」そんな視点で、このクマ対策パッケージを眺めてみたいところです。
野生動物からの被害を未然に防ぐため、目撃・痕跡情報をわかりやすく掲載し、住民・観光客などに向けて注意喚起する『アニマルアラート』の導入を、自治体様向けに募集しています。
⇒『アニマルアラート』の詳細はこちら