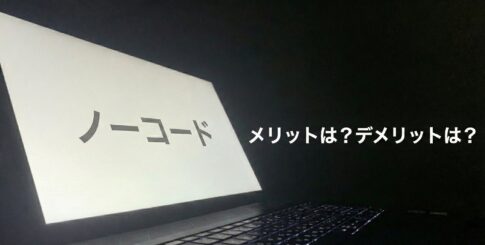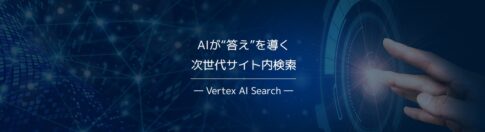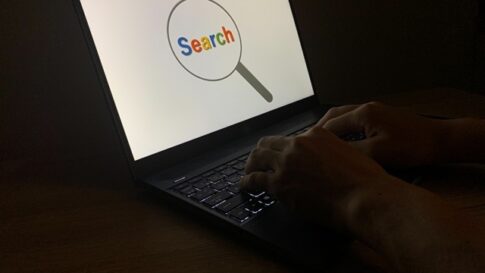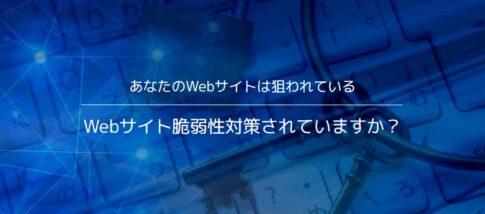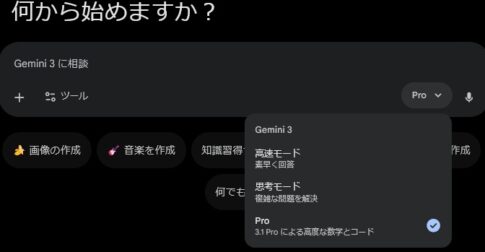生成AIは“答えを返す”から“仕事をこなす”道具へ。AIエージェント化の波で、単純作業は確実に縮小しています。一方で“AIに働いてもらう準備と監督”という新しい職種が静かに増えていることはご存じですか?
「AIが自分でブラウザを動かす」時代に
2025年、OpenAIが発表したChatGPTのエージェントは、指示に応じて自らブラウザを操作し、手順を計画し、完了まで走り切るタイプのAIです。例えば、観光プラン作りからフォーム入力の自動化まで、人がやっていた“PC作業”の丸ごと代行が現実味を帯びました。OpenAI+1
この変化は「問い合わせに答えるAI」ではなく、「業務の実行者になるAI」への移行です。結果として、定型の入力・転記・一次対応といった仕事は真っ先に自動化の対象になります。実際、AIを理由としたレイオフ件数の増加を伝える報道も出ています。forbes.com
一方で、ルールづくりと監督の重要性は増すばかりです。EUのAI法は、リスクに応じた管理や記録義務を企業に課し、特に汎用AIについて具体的なガイドラインを整備中です。ここから、AIの運用と適合性を担保する人材の需要が読めます。digital-strategy.ec.europa.eu+1
減りやすい仕事、増えている/生まれている仕事
減りやすい仕事
- 一次カスタマーサポート/FAQ対応:自然言語での自動応答+画面操作の自動化で、24時間体制が可能になります。
- データ転記・資料整形・定型レポート:RPA(作業自動化)と生成AIの組み合わせで“人手の作業時間”が圧縮します。
- 簡易なリサーチ・比較表づくり:エージェントが収集→要約→表化まで行えるため、アシスタント的タスクは、かなり縮小するのではないでしょうか。
さらに、事務・ 事務補助職は影響が大きいと思います。とりわけ女性比率の高い職種でAIの影響が強いと思われるため、配置転換や再教育を急がせそうです。
増えている/生まれている仕事
- AIオペレーター(エージェントを運用していく仕事):
業務手順を設計し、権限や入力範囲を安全に絞り、失敗時のリカバリを決める“現場の指揮者”です。プロンプトだけでなく、「タスク分解→検収→ログ監査」までを見る役割です。OpenAIのエージェント登場で一気に具体化していきます。OpenAI - AIコンプライアンス/リスク管理:
モデルの出力記録、データ来歴(どこから来たか)、高リスク用途の審査など。AI法対応を機に内製ニーズが拡大していきます。調査ではAIコンプライアンスや倫理の専任採用が進んでいるとの報告もあります。McKinsey & Company+1 - 評価者(モデル・プロンプト評価):
出力の品質を点検し、テストデータ(時に合成データ)で穴を見つける人たち。自動化しづらい“判断の質”が問われる領域です。 - ワークフロー設計者(業務×AIの織り込み):
既存システムやRPAとAIエージェントの“受け渡し”を設計。セキュリティと運用の落としどころを作る役割です。 - 事業ドメイン×AIのハイブリッド職:
医療事務×AI、法務×AI、広告運用×AIなど。現場の文脈を知り、AIに“仕事のコツ”を教える翻訳者です。
スキル面のシフト(専門用語は噛み砕くと…)
- 手順設計(オーケストレーション):仕事を「小さな手順」に分け、AIに渡す順番を決める設計力。
- ガバナンス:記録を残し、誰が何を許可したかを説明できる状態を保つこと。
- 評価設計:良い出力・悪い出力を具体例で定義し、テストを回す力。
- 人間中心の体験設計:全自動に“確認ポイント”を挟み、ミス時に人が素早く引き継げる線引き。
決して「なくなる仕事=価値がない」ではない
私が見聞きして感じるのは、「なくなる仕事=価値がない」ではないということです。むしろ、価値はあるのに手続きだらけだった仕事が、AIの得意領域と重なっているだけだと思います。そこで人は何をしていくべきか、ということではないでしょうか。3つ挙げてみます。
- 作業から設計へ寄せる
受け身で“来た仕事を処理する”人から、「仕事の段取りを決める人」になる。小さなチームの自動化でも、役割はガラッと変わります。 - ログと評価を味方にする
AIは根拠の説明が苦手です(いまのところ・・)。プロセスの記録と検収のルールを整えた人が、組織の信頼を握ります。EU AI法対応の有無に関わらず、日本企業でもここは差が出るはずです。 - 事業ドメインの知識を芯に据える
「現場の文脈×AI」を持つ人は強いです。たとえば広告ならKPI(何を成果とみなすか)の定義、医療ならカルテの読み筋。AIに教える現実の常識を伝えられることが武器です。
段取りよく、安全に、検品できる人は、どんな肩書になったとしても食べていけると思います。
AI活用に悩む経営者・マネージャーの方へ。Web制作の現場を知る、元アートディレクター・営業の視点で、AIの活用方法についてサポートします。
⇒生成AIセミナー・個別相談はこちら