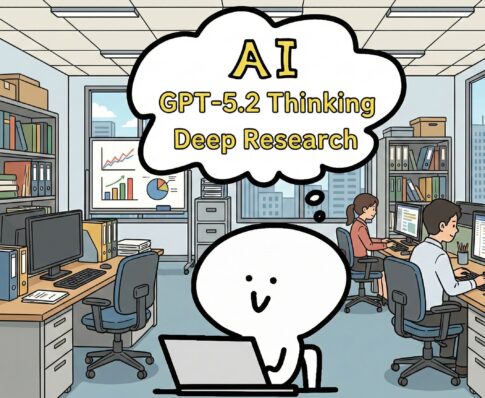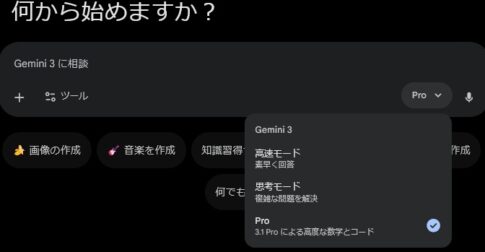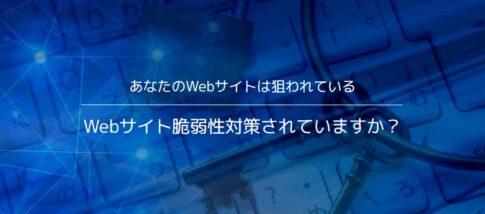生成AIは、事務的な業務だけでなく音楽・デザイン・動画などの“ものづくり”の現場にも広がっています。いま現場で何が起きているのか、そして私たちはどう動けばいいのかを挙げていこうと思います。
いま何が起きている?
争いから合意へ:大手レーベルがAI音楽サービスを訴える流れがあったのですが、それを許可することで使えるようになるかわりに、お金を分配する方向になってきました。作られた音はサービスの中だけで使う(ダウンロードは不可)など、レギュレーションを明確にして、不本意な広がりすぎを防ぐ仕組みも考えられてきています。
みんなが安心して遊べる場づくり:これも音楽ですが、ファンが音を合法的にリミックスでき、アーティストにもちゃんと報酬が行く道すじが見えつつあります。グレーだった二次創作をOKのルールの中に入れる動きというわけです。
ツールはますます便利に:Adobeなどでは、画像・動画・音をまとめて作って編集できるようになりました。ただ、手作業は減る一方で、同じような作品が増えやすいという課題も出ています。
AI利用のルールがはっきりしてきた:例えばEUでは、AIがどんなデータで学んだかの要点を出す動きが進んできました。中身の見える化を進めることによって、信用を得るという発想からだと思います。
クリエイターの仕事はどう変わる?
1)仕事の分担が変わる
- これまでは「1曲まるごと」「1本の動画まるごと」を人が作ってきました。
- これからは、アイデアを言葉にする→AIの結果を選んで直す→使い方の約束を決める、という三つの役割に分かれていくと思います。
2)“その人らしさ”の価値が上がる
- 使用するツールが同じなら、見る人聴く人が「この人らしい」と感じる声や視点が価値の差になります。例えば、個人的な体験や調べた奥深い知識などは真似されにくい宝物です。
3)ギャラは二つのゾーンに分かれやすい
- ギャラ低め:テンプレ的な生成+軽い手直し(早い・多い)。
- ギャラ高め:アイデア作りからブランドの文脈、権利の整理まで入った丸ごと支援。
4)素材の出どころ管理が日常の仕事になる
- 出どころがはっきりした素材(自社データ、許可済みライブラリ、合成音など)を使い、作成の記録を残します。
- でき上がったものの使ってよい範囲(商用/非商用、ダウンロードOKか、など)を、契約や利用規約に明記するようになります。
5)運用面
- 国や地域でルールが違うので、グローバルに手掛けている人は、地域ごとの運用を用意しなくてはならなくなるでしょう。
- 制作会社も、モデルやデータの出どころを説明できる体制が、仕事をしていく上での強みになります。

AIに置きかわるとか置きかわらないとかの二択ではない
現場は、AIに置きかわるとか置きかわらないとかの二択ではないと思います。置きかわるのは作業の一部で、置きかわりにくいのは判断と人とのやりとりなのは間違いありません。例えば、
- 企画の問いの立て方(何を作るのがいちばん役立つか)
- 作品のトーンをそろえること(世界観やトンマナ的なこと)
- 権利や配信などまで含めた現実的な落としどころ
このような場合は人の出番です。
まず、何のために作るのかを短く言葉にする習慣が、仕事をする上で大切なのではないかと思います。AIは強い相棒ですが、進む方向を決めるのは私たちです。どんなクリエイティブな仕事でも、世に送り出すことを決めるのは人、つまりクリエイターの仕事なのです。
AI活用に悩む経営者・マネージャーの方へ。Web制作の現場を知る、元アートディレクター・営業の視点で、AIの活用方法についてサポートします。
⇒生成AIセミナー・個別相談はこちら